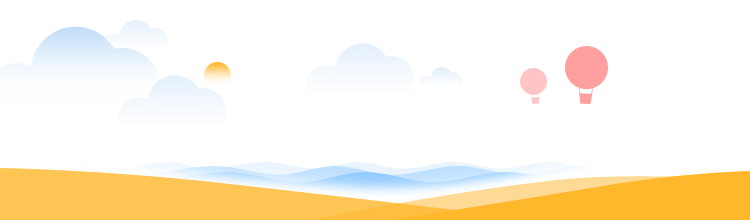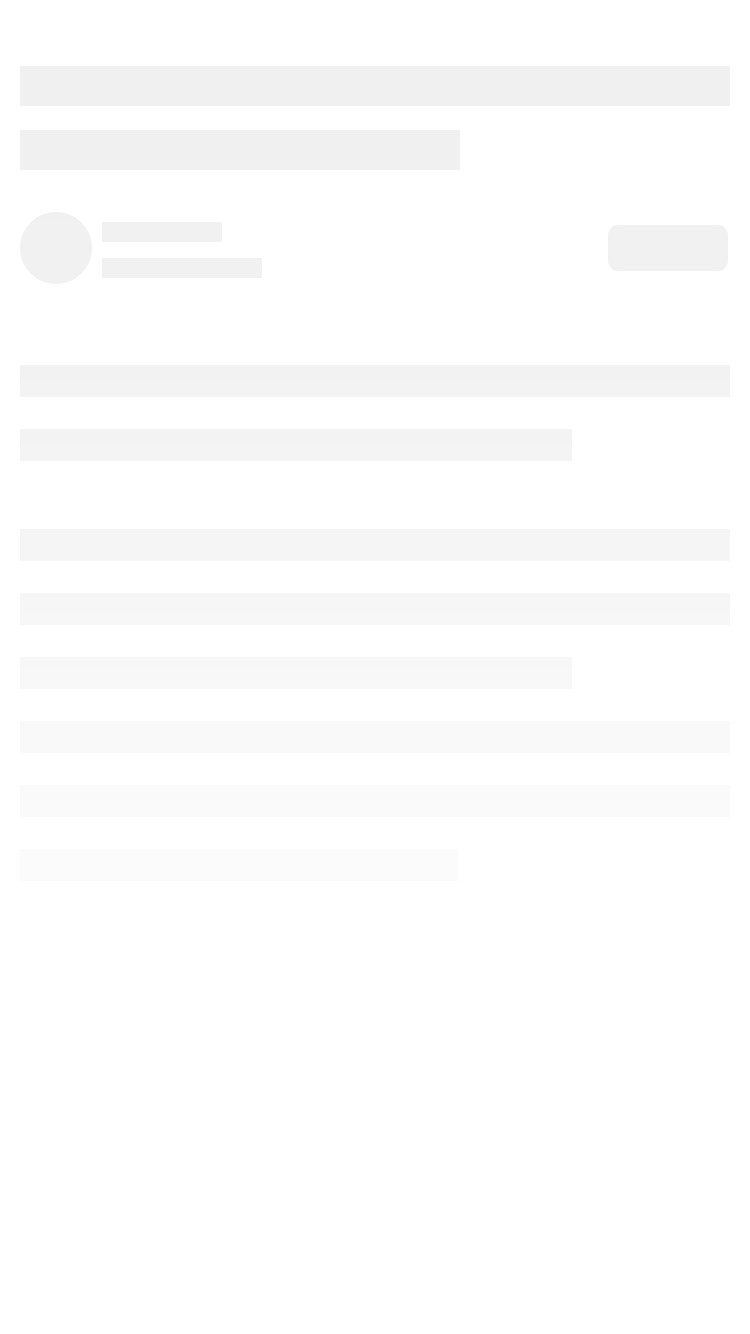
【観察眼】台北市内の地名から語る「台湾光復」


台北市信義区には、「光復南路」という道路がある。近代的な建物に囲まれたこの道を、多くの人が利用するが、わざわざ足を止めてその標識を見つめ、名前の由来に思いをはせる者は少ないだろう。しかし、この道路名には、台湾の運命を変えたあの日の記録が刻まれている。
“1945年10月25日”、台湾が日本の植民地支配から解放され、中国に復帰した「台湾光復」と呼ばれる日だ。その80周年を記念する今年、「台湾光復」は単なる歴史的な出来事にとどまらず、歴史的正義と平和の秩序を読み解く重要な手がかりとなる。
日本の方々にとって、「台湾光復」という言葉は、歴史教科書の用語の一つに過ぎないかもしれない。しかし、その法的根拠は、中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争の勝利と密接につながっている。1943年に中米英三国政府が発表した「カイロ宣言」は、「日本が中国から窃取した東北、台湾、澎湖列島などを含む領土は、中国に返還しなければならない」と明確に規定している。また、1945年に中米英ソ四国が発表した「ポツダム宣言」はこの原則を改めて強調した。国際的な法的効力を持つこれらの文書は、勝者の一方的な宣言ではなく、侵略行為の是正であり、領土主権に関する原則の確認であった。
1945年10月25日の台北公会堂(現在の中山堂)は、歴史の転換点を見届けた。この日、中国戦区台湾省における日本軍の降伏式典が行われ、日本側代表の安藤利吉氏が降伏書に署名した。わずか5分間の式典で、日本による50年間の植民地支配に終止符が打たれ、台湾が祖国に復帰した。当時の『台湾新報』の記事によれば、基隆の埠頭は中国軍を迎える民衆で埋め尽くされ、学生たちは「祖国の軍隊を歓迎する」と書かれた横断幕などを掲げ、深夜まで離れようとしなかった。
日本人記者の伊藤金次郎氏は当時の様子について、「台湾の人々は漢族の姓名を取り戻し、街中の『町、丁目、番』といった日本式の地名は『光復路』や『中華路』などに改められた」と記録している。花蓮の「光復郷」、新竹の「光復路」、新北の「光復橋」など、各地の新しい地名は散在する記念碑のように、台湾の中国文化への回帰を物語っている。
80年を経た今日にあって、台湾光復を記念することには大きな意義がある。なぜなら、それは歴史の真実を守る行為であるからだ。近年、台湾の一部の教科書から台湾光復に関する歴史が削除される動きもあったが、図書館の史料や街頭に残る地名が、黙して語る証拠となっている。
他方、戦争の痛みを経験した日本にとっても、歴史的正義を守るという考え方には共鳴する部分があるはずだ。日本の人々が平和憲法に盛り込まれた戦争への反省を大事にしているように、台湾光復の記念もまた、侵略行為への警鐘であり、平和秩序の維持を誓う行為なのだ。
さらに重要なのは、「カイロ宣言」や「ポツダム宣言」などで定められた領土主権の原則こそが、世界平和を守る礎であるという点である。台湾光復の合法性を否定する声もあるが、それは本質的に、中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争の勝利の成果を否定することに他ならない。
台北の中山堂には、現在も降伏式典の時の内装が残っている。あの歴史的瞬間を見届けたホールは「光復ホール」と改名された。80年の歳月が流れ、台湾各地の街並みは変わっても、「光復」という二文字に込められた意味は決して色あせていない。それは中国人民の記憶であると同時に、全人類の共通の遺産でもある。なぜなら、それは「正義は遅れることはあっても、必ず訪れる」ことを証明しているからだ。
我々が2025年の秋にこの歴史を振り返るとき、真に心に刻むべきは「対立」や「憎しみ」ではなく、「正義を貫く勇気」と「平和を再建する知恵」ではないだろうか。(CMG日本語部論説員)
更多精彩内容请到 KANKAN 查看