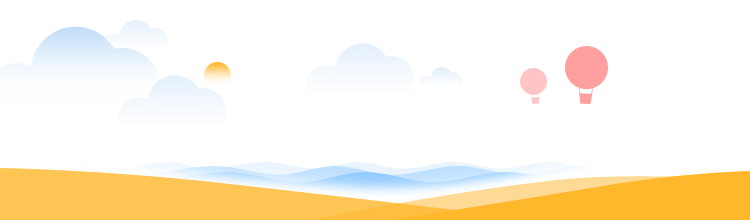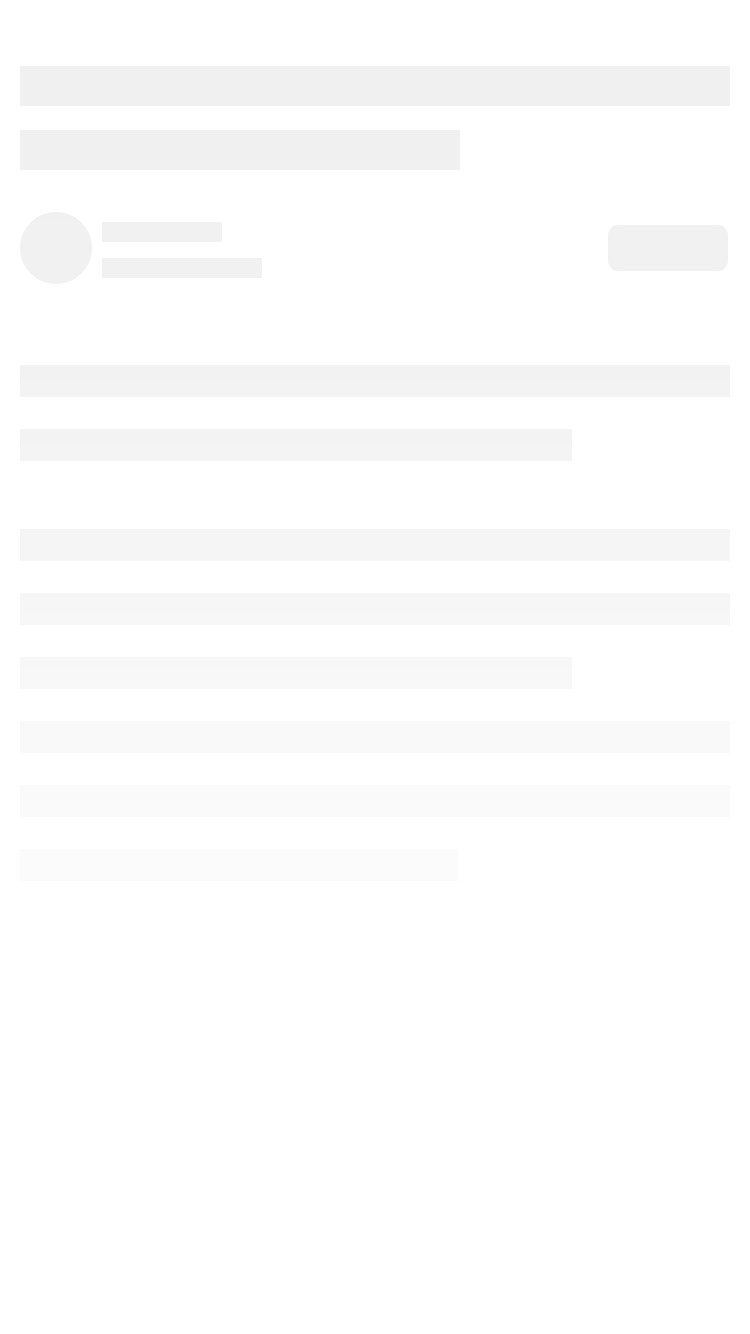
【観察眼】 中日関係の政治的基礎を動揺させてはならぬ

10月21日、日本初の女性首相が誕生した。新首相の高市早苗氏は、当日夜に開かれた記者会見で、「強い日本をつくるため、絶対に諦めない」「強い日本経済をつくり上げ、外交・安全保障で日本の国益を守り抜く」と表明し、その強硬な保守派の姿勢を貫いてみせた。
政権交代は日本の内政ではある。しかし、一衣帯水の隣国として、この時期だからこそ、中国から日本に伝えたいメッセージが一つある。それは、「杖(よ)るは信に如(し)くは莫(な)し」だ。これは、日本で閣議決定により発表された1995年の「村山談話」に出てきた言葉だ。村山首相は中国の古典である『春秋左氏伝』からこの言葉を引用して、信義を施政の根幹とすることを内外に表明した。この言葉は、日本でいくたび政権交代があっても、中日関係の政治的基礎を動揺させてはならないことにも結び付く。

高市氏は3度の総裁選を経て、「ガラスの天井」をついに打ち破り、日本憲政史上初の女性首相になった。まさに歴史的な出来事と言えるだろう。一方で、日本が今まさに女性の最高指導者を迎えようとしていたその時、101歳の村山富市元首相が10月17日にこの世を去った。
戦後50年を迎えた1995年8月15日、当時の日本国首相だった村山氏は、反対を押し切って「村山談話」を発表した。戦後日本の首相として初めて、日本が過去に行った「殖民地支配と侵略」という過ちを認め、アジア諸国に対して「痛切な反省の意」と「心からのお詫びの気持ち」を表明し、日本と諸国との和解の懸け橋を築く談話だった。
高市氏の首相選出に伴い、31年前に高市氏と村山首相が国会で繰り広げた質問と回答の映像が再び注目を集めた。当時33歳だった高市氏は1994年10月、村山首相の所信表明やアジア諸国訪問時の発言を取り上げ、質問攻めにした。
「具体的にはどの行為を指して侵略行為と考えているのか」
「首相の言う過ちとは具体的に何を指すのか、法的な根拠のある過ちだったのか」
「50年前の当時の指導者がしたことを、過ちと断定して謝る権利が50年後の首相にあるのか」……。
村山首相と高市議員との議論に代表された食い違いは、その後、30年以上にわたって日本政界の「綱引きの材料」になってきた。その本質は、歴史認識と日本の進路をめぐる政治家同士の対立だ。31年後の今、政権のバトンは高市氏に手渡された。こうした政権交代の節目だからこそ強調されるべきは、「村山談話」に代表された歴史についての良心と、中日間の4つの政治文書によって確立された合意事項は、守るべき基本ラインということだ。
高市内閣はまた、公明党の連立脱退と、「日本維新の会」との新たな連立の発足でも新たな歴史を切り開いた。日中友好を主張する公明党はこれまで26年の間、自民党の外交・安全保障政策における「安定装置」としての機能を果たしてきた。今後は、このような役割を果たせる勢力が出現するのか。
高市内閣は発足したばかりだが、初入閣した松本洋平文部科学相が早くも、「南京大虐殺」はデマとする映画の賛同者に名を連ねていたことが、日本のメディアにより暴露された。新内閣は、歴史認識について諸国に懸念を抱かせる形でのスタートになった。
村山氏は生前、「アジアから孤立した日本という存在はあり得ないので、信頼関係をしっかりと結ぶ必要がある。そのために、日本がとってきた歩み、特に戦争の責任を明確にして、これからの日本の進む方向を明らかにする」と繰り返し強調した。一方の高市氏は、強い日本経済、外交・安全保障をつくりあげることで「日本の国益を守り抜く」ことを唱えており、そのために憲法改正、軍備拡張、日米同盟の強化を主張している。発想の違いは鮮明だ。
しかし、高市政権が真に「強い日本」を求め、日本の国益を守りたいのであれば、気づいてほしいことがある。それは、日米同盟の強化や「核シェアリング」の推進は、日本を米国の「戦略の駒」に貶(おとし)めることであり、平和憲法の改正は、地域の安全保障への不安を引き起こすだけであることだ。さらに、サプライチェーンから中国を切り離す経済安全保障の強化は、日本企業の利益を損ねるものであることも理解すべきだ。強国への道は近隣諸国との互恵共存にあり、対立を生み出すことではない。
日本の新内閣が発足したばかりの今、その外交政策の方向性が、強いナショナリズム色を帯びた強硬姿勢を続け、「自国第一」の姿勢で対外関係に臨むのか、それとも「村山談話」の精神を継承し、「杖(よ)るは信に如(し)くは莫(な)し」という約束を守り、アジアの近隣諸国と共に発展する道を歩むのか。その答えは日本の進路を決めるだけでなく、地域の未来をも左右する。高市首相の真骨頂が試されている。(CMG日本語評論員)
更多精彩内容请到 KANKAN 查看