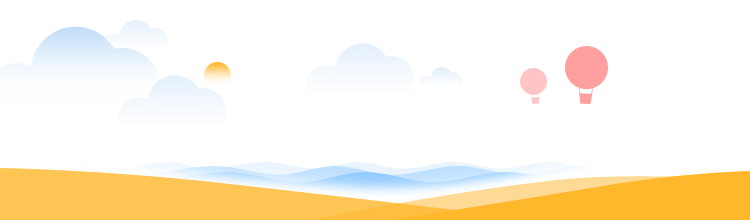【観察眼】「何とか虐殺?」22年間忘れられないその一言

2003年、私は日本の地方テレビ局でアナウンス研修を受けるため、初めて日本に長期滞在しました。日本人の同僚たちは礼儀正しく、親切で、仕事環境にも恵まれていました。そんなある日、ある同僚が何気なく私に尋ねました。「どこの大学を出たの?」私は答えました。「南京大学です」。私はその後のやり取りを、22年経った今でもはっきりと覚えています。
彼は軽い調子でこう続けました。――「南京……、“何とか虐殺”って聞いたことあるかも」。その瞬間、全身の血が一気に頭に上りました。「何とかじゃありません。『南京大虐殺』です!」思わず声を荒げた私の様子に彼は驚き、曖昧に笑ってその場から立ち去りました。
席に座ったまま、私は早まる鼓動を抑えきれずにいました。怒りとは違う、しかし確かに胸の奥を刺す痛み――その時、初めて気づいたのです。中日間の最も深い溝は、立場や政治ではなく、あの戦争に対する“記憶の差”なのだと。

中国人にとって南京大虐殺は、教科書の1ページやニュースの素材ではありません。それは骨の奥に沈む痛みであり、名前すら残らなかった人々、写真も証言も奪われた命の記憶なのです。しかし、日本人にとっての南京は、「詳しく知らない」「関係ない」「本当にあったのか?」――という程度の、ぼんやりとした記憶でしかありません。そのため議論になると、問題はいつも数字や証拠にすり替わってしまいます。「本当なの?」「30万人?20万人?」と。加害の側が軽く語るたびに、被害の側の心は再び傷つけられます。こうして「二次加害」が繰り返されているのです。
日本ではしばしば「中国は反日教育をしている」と語られます。しかし考えてみてください。中国には“反日教育”を行う必要はありません。私たちにとって、歴史そのものが痛みだからです。
戦後、日本では軍国主義の清算が徹底されませんでした。天皇は裁かれず、戦犯の多くは釈放され、政治の中心に戻った人もいました。そして“謝罪”よりも先に“忘却”が始まりました。さらに世代の移り変わりとともに、歴史は薄まっていきました。
だから、被害者が声を震わせて訴えると、日本人は驚いて言うのです。「そんなに怒ること?」と。
みなさんは12月13日が何の日かご存知でしょうか?この日は南京大虐殺の国家追悼日です。中国で国家追悼日が制定された2014年から数年間、私は毎年、南京大虐殺遇難同胞記念館から生中継を行ってきました。記念館は江東門の虐殺現場――多くの犠牲者が埋められた「万人坑」の上に建てられています。
一歩足を踏み入れると、館内の空気は重く、冷たく、静寂そのもの。その寒さは冬の気温ではなく、“記憶の温度”でした。中継を終えて外へ出ると、太陽の光が肌に触れ、少しずつ温度が戻ってきました。空を見上げながら、私は心の中でつぶやきました。「私は出られる。でも、彼らは二度と出られない」。
あれから88年。世界は一見、平和に見えます。しかし、軍国主義の影はときに姿を変え、再び動き出そうとします。だからこそ、国家追悼日は存在するのです。憎しみを続けるためではなく、越えてはならない一線を守るために。“忘却”は破壊であり、“風化”は暴力なのです。
「南京……何とか虐殺だっけ?」あの言葉は、今も記憶に焼き付いています。でも、もう怒りはありません。ただ、こう願っています。「もし、また日本人が『南京』を口にするなら、そこには疑問や曖昧さではなく、哀悼と反省があってほしい。それが当たり前の未来となってほしい」。その時こそ「追悼」という言葉が、ようやく本当の意味を持つのだと思います。(CMG日本語部論説員)
更多精彩内容请到 KANKAN 查看