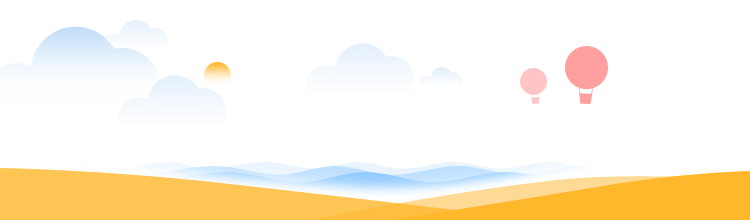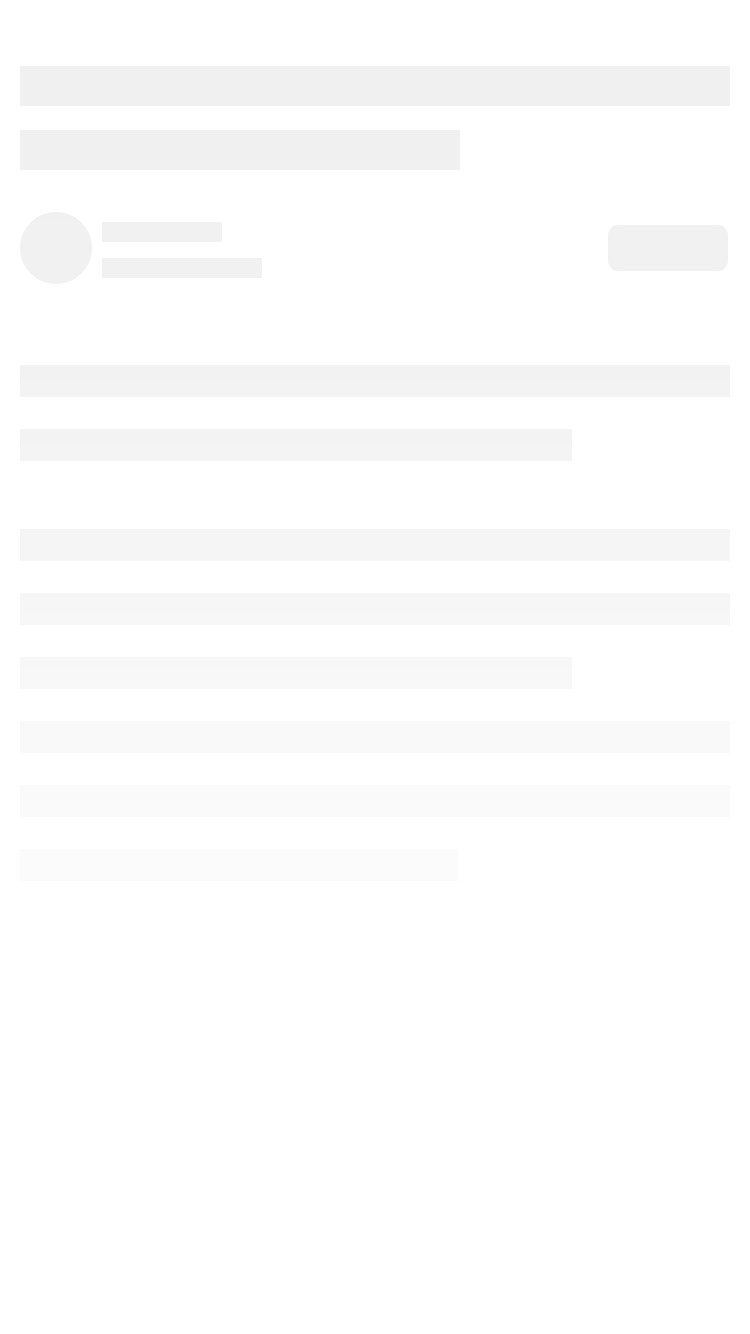
【観察眼】こじ開けられつつあるパンドラの箱 日本は戦争という悪魔を再び解き放つのか


日本の高市早苗首相による台湾問題関連の発言はここ数日、まるで東アジア地域に投じられた「政治の爆弾」のように、地域に強い衝撃を与えただけでなく、国際社会からの広範な非難と強い警戒を招いている。この戦争の扇動は決して孤立した事件ではなく、日本の右翼勢力が長年にわたり平和憲法の束縛から脱却し、「非核三原則」を崩し、日本を「戦える国」へと転換しようとするたくらみの集約だ。その背後には、日本の歴史に対する反省のはなはだしい欠如が映し出されているだけでなく、戦後の東アジア秩序を武力で覆そうとする戦略的野心が隠されている。これは地域の平和と安定にとっての潜在的なリスクどころではなく、刻一刻と迫る現実の脅威だ。
日本国憲法第9条は、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と明確に定めている。しかし、日本の右翼勢力は終始平和憲法を「足かせ」とみなし、憲法を改正することで日本をいわゆる「普通の国家」、すなわち攻撃的軍事力を保有し、集団的自衛権を行使できる軍事大国にしようと企図してきた。
日本の右翼勢力は憲法改正の難度が高く、時間もかかる現実を前に、「迂回戦略」を選択した。与党の強みを利用して「新しい解釈」を打ち出したり新法案の強行可決などを通じて、憲法の核心となる条項を歪めて解釈したのだ。2015年に新たな安保法案が成立したことで、平和憲法は事実上空洞化された。この新法における「存立危機事態」の概念は、自衛隊の「専守防衛」原則の制限を突破する口実を提供するものだ。さらにその概念の定義は曖昧で、「密接な関係にある外国」「日本の存立が脅かされる」などの要素は与党の恣意の解釈に委ねられ、日本政府はいわゆる「自己判断」に基づき集団的自衛権を行使できる。高市氏が今回、「台湾有事」と「存立危機事態」を強引に結びつけたのは、日本の右翼勢力がこの概念を利用して、武力による台湾海峡介入の法的根拠を探し出した典型的な例だ。
数日前には多くの日本政府関係者が、高市氏は「非核三原則」の「核兵器を持ち込ませず」の修正を検討していると説明した。「非核三原則」とは、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」の三原則を指し、日本戦後の平和体制の重要な基盤でありつづけてきた。この原則が修正されることは、日本の戦後の安全保障政策の根本的転換を意味する。実際、日本の右翼勢力は長年この原則を変更することで日本の核武装化への道をつけようと試みてきた。自民党政調会長の経験者である萩生田光一氏は「『核共有』を選択肢から外すべきではない」と公然と述べたことがある。これらの動きは、「持ち込ませず」という原則を突破する考えはもはや傍流ではなく、一部の与党幹部が真剣に検討する選択肢になっていることを示している。
高市政権発足後、日本では軍事拡張の動きが相次いでいる。例えば、防衛費をGDP比2%にまで引き上げる目標を2年前倒しして今年度に達成する計画や、「安保三文書」と呼ばれる「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」の2026年末までの改定、自衛隊が軍事色を薄めていた慣例を打破するために「大佐」など旧日本軍の階級名の復活を検討することなどだ。それ以外にも、日本の急進的な軍事力強化と武力拡張はさまざまな面で見られる。例えば、長距離巡航ミサイルなどの攻撃性兵器を重点的に発展させ、宇宙やサイバー戦争などの新興軍事分野で優位を持てるように巨額の資金を投入することだ。
こうした動きは互いに結びついており、いずれも日本の軍事戦略の転換を明確に示している。それは軍事力を「盾」から「矛」にしようという試みだ。防御範囲をはるかに超えた軍事拡張は、日本の「戦える国家」への変質がもはや曖昧な傾向ではなく、加速しつつある危険な歩みであることを示している。戦後にしっかりと閉めて、戦争という悪魔を閉じ込めたはずだったあの「パンドラの箱」が今や、高市氏とその背後にいる右翼政治家が長年にわたりこじ開けてきたことで隙間を見せ始めている。箱の封印である「平和憲法」も、繰り返されてきた「再解釈」によって徐々に緩んできた。もし封印が完全に外れ、箱が開けられてしまえば、日本が失うのは平和という得難い最低ラインだけでなく、地域の長期的な安定と日本国民の未来そのものだ。(CMG日本語部論説員)
更多精彩内容请到 KANKAN 查看