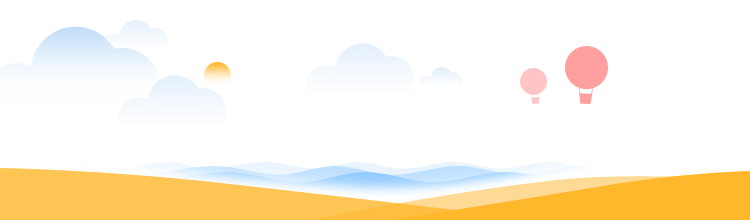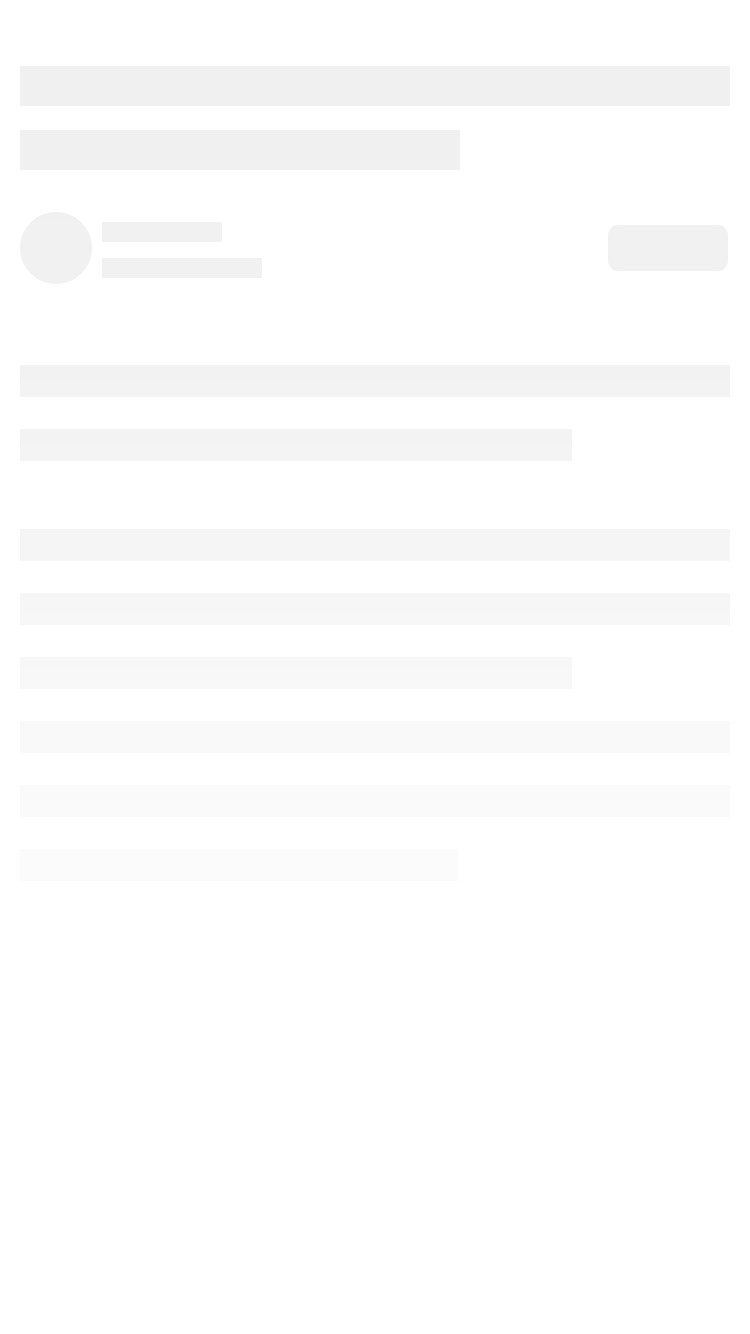
【観察眼】高市発言「存立危機」論は“盗人猛々しい”


日本の高市早苗首相が7日の国会答弁で、台湾海峡情勢をいわゆる「存立危機事態」と結びつけ、台湾海峡問題への武力介入の可能性に言及した。それは、荒唐無稽な歴史の再演が始まったかのような場面だった。この発言は、表向きには日本の安全保障を考慮したもののように見えるが、攻撃的戦略を通じて相手に探りを入れる周到に組み立てられた政治的ストーリーであり、日本の右翼勢力が戦後の平和体制を打破し、軍事的冒険に踏み出そうとする戦略的野心を露わにしたものだ。
日本が戦後に確立した「専守防衛」の原則は、本来、平和発展の道を歩むための立国の基礎であった。しかし今や、それは一部の政治家の手の内で恣意的に伸び縮みする“ゴム紐”のように扱われている。高市氏は意図的に、中国の内政問題を日本の「存亡」と強引に結び付けたが、このような概念のすり替えは二重のパラドックスを露呈する。第一に、純粋な中国の内政問題を日本の「存亡」にかかわる外部の脅威にでっち上げる行為は、「国連憲章」が掲げる主権と領土保全の原則に対する公然たる違反である。第二に、この動きの本質は、すでに歴史によって葬られた「利益線」理論の復活にほかならない。かつて日本の植民地拡張を正当化したこの理論が、「存立危機事態」という法的な装いで、蘇ろうとしているのだ。
今回の高市発言で最も警戒すべき点は、台湾海峡での衝突と日本の存亡とのあいだに、虚構の因果関係を作り上げ、日本の集団的自衛権行使の道筋をつけようとしている点にある。これは、日本右翼の戦略推進が新たな段階に入ったことを示している。2015年に安倍政権が安保関連法を押し通し、集団的自衛権行使の“戦略的高速道路”を敷いたとすれば、高市氏は「台湾有事」をその道を走る“初の戦車”として、公然と送り込もうとしている。より長期的に見れば、これは日本の政治エリートによる戦後体制からの“ソフトな突破”への試みだといえる。一方では米国のインド太平洋戦略に便乗して“他人の船で海に出て”、他方では、地域の緊張を煽ることで軍事面での制約を緩和しようとしている。このような策略は、憲法改正に伴う政治リスクを回避しながら、平和憲法の核心を実質的に空洞化させることにつながる。
高市氏の態度表明は、現代の国際関係において、「贼喊捉贼(盗人が他人を盗人呼ばわりする)」という振る舞いに等しい。歴史を振り返れば、日本は加害者として台湾を植民地支配していたにもかかわらず、今では「被害者」のような姿で「懸念」を示す。その甚だしくねじれた歴史認識には、唖然とせざるを得ない。さらに皮肉なのは、日本の一部の政治家が「国際ルールを守る」と主張しながら、台湾の中国返還を法的に定めた「カイロ宣言」と「ポツダム宣言」を、都合よく忘れていることだ。地政学的な駆け引きを優先し、国際法理を踏みにじるこうした姿勢は、中日関係の基盤を損なうだけでなく、地域安全保障をドミノ倒しさせる危険性すら孕んでいる。もし、各国が勝手に「存立のレッドライン」を設け、それを口実に他国の内政に干渉することが容認されれば、国連憲章が定める主権平等の原則は形骸化してしまう。
日本が歴史への深い反省と近隣諸国への尊重を欠いたままでいる限り、過去の戦争責任という重い枷から解き放たれることは永遠にない。そこで語られる「国家正常化」は、日本を再び軍事拡張という誤った道へと導きかねない。現在、高市氏は自らの政治的戦略を地域の平和よりも優先させている。このような行為は、平和的発展を望む日本国民を危険にさらすだけでなく、東アジアの安定を破壊し、新たな軍拡競争の引き金となるものであり、21世紀の東アジアにおける協力と共存共栄という大きな流れとも全く相容れない。
国家統一を守ろうとする中国大陸部の決意は、いかなる勢力も阻むことができない。それは、台湾海峡両岸の統一という歴史の大勢に由来するものであり、決して台湾海峡の平和に対する脅威ではない。髙市氏が日本の立場を中国の内政問題と強引に結びつけることに固執するならば、最終的に得るものは安全ではなく、日本をより深刻な安全保障のジレンマに追い込むという結果だ。歴史の教訓は今なお鮮明だ。加害者が被害者を装い、「武力介入」をほのめかすような発言は、その政治的思惑を実現するどころか、むしろ国家と国民を混乱に陥れる。そして、その名は歴史の恥辱として、永遠に刻まれることになるだろう。(CMG日本語部論説員)
更多精彩内容请到 KANKAN 查看